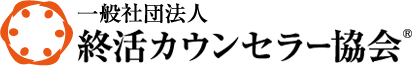怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記㊲ 何歳からおじいさん?

高齢者は何歳以上か。実は一律の定義はない。
「高齢社会対策基本法」「老人福祉法」にも年齢は出てこない。
わが国では習慣的に65歳以上としている。
「高齢化率」が28.4%で記録を更新した。
15年後にはさらに33.3%に増加する見込みという。
これは総人口に占める65歳以上の者が占める割合のこと。
寿命が伸びれば高年配者の数が増える。
65歳の年齢を固定し計算すれば高齢化率の増加は当然である。
平均寿命の延びなどに合わせて定義年齢を変えれば、数値は大きく変わる。
若いと思っていたけれど、ある日、自分は高齢者とか老人に区分されるべきと感じるのは何歳からだろうか。
電車内で吊革につかまっていたら、「おじいさん、腰かけませんか」と席を譲られるようになったときではないかという気がする。
国内では未経験だが、国民全体が若いイメージの途上国で、何年も前に経験した。ボクの年齢はその国では十分に高齢者であり、日本ではまだ若造というだろう。
 日常生活に制限を伴うようになる平均年齢を「健康寿命」という。
日常生活に制限を伴うようになる平均年齢を「健康寿命」という。
これを超える者を高齢者と定義するのが一つの見識かもしれない。
この提案が採用されれば、2016年時点の健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳であるから、73歳あたりが現時点での高齢者仲間入り年齢となり、基礎年金の支給開始年齢や高齢者医療への加入替え年齢を連動させればよいことになる。
人は年齢より若いと評価されれば喜び、逆だと憤慨する。
社会保障給付においてのみ、無理に老人扱いする必要はない。
高齢社会白書2020年版によると、収入ある仕事をしている男性の比率は、60代後半60.1%、70代前半の41.7%から70代後半28.8%へと急減する。この数値からも75歳の少し前あたりで区切るのが妥当な気がする。

終活カウンセラー協会顧問 喜多村悦史
元経済企画庁総合計画局計画官
元社会保険庁企画・年金管理課長/元内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官
東京福祉大学・大学院 副学長兼教授
1951年広島県福山市生まれ。京都大学法学部卒。
1974年厚生省(現厚生労働省)入省。
保険局、年金局、保健医療局等で社会保険制度の企画・運営等に従事。
生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長、生活衛生局企画課長、
内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官等を歴任
2020年09月07日