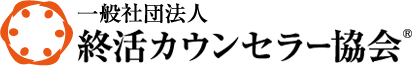怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記122 “たくぼ”ってなんだ
 「骨まで愛して」。そんな題名の流行歌があった。
「骨まで愛して」。そんな題名の流行歌があった。
その通りに実践する方法がある。愛する人が亡くなった。その火葬後の焼骨を、少しずるかじりつつ、故人を偲ぶ。
そこまではちょっと、という人に受け入れられそうなのが、お墓を部屋の中に設置して朝晩、経をあげる方式。自宅の屋内に設置されたお墓なので、宅募(たくぼ)と呼ぶことになる。滋賀県の石材メーカーが売りだし、実際に売れているという(朝日10月14日)。
墓地は高いし、遠い。老齢の身に墓参は辛いし、自分亡き後、引き継ぐ人がいない。そこで考えられた方式だという。
屋内の茶箪笥の上などに置くのだから、コンパクトでなければならない。取材例では小さな四角な石(高さ約14㎝、幅約12㎝、奥行き約12㎝)。石には直径6㎝、高さ7.5㎝の骨つぼが入る穴が開き、線香立ても付いている。
手元供養協会(京都)は「経済的に余裕のない高齢者が増え、お金をかけずに供養できる動きが時代に合っている」、全日本仏教界(東京)は「地方では寺の跡継ぎがおらず、墓地の管理に困る地域もある。地域の実情に合わせた墓があってもいいのではないいか」とコメントしたようだ。
だが、記事に書かれえていない部分に問題がありそうだ。火葬場から持ちかえる骨つぼの焼骨を、宅墓の骨つぼ(直径6㎝、高さ7.5㎝)に移すことになるが、入りきらない骨をどうするのか。
所有者が亡くなった後、宅墓内の骨つぼと焼骨をどうするのか。
わが国の葬送文化を律する法律(墓地埋葬法)によれば、焼骨は最終的に墓地内に収蔵され、風化して土に還すことになっている。
顧問 喜多村悦史
2020年12月01日