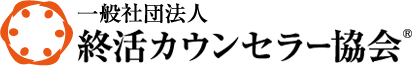怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記154 ご飯とテレビゲーム…
幼稚園児がゲーム機の虜になっている。ごはん時になってもゲーム機を離さない。ゲームをしながら食べようとする。
「食べるか、ゲームするかどちらかにしなさい」と注意したら、「ゲームをする」と食卓から離れる。
「食事もおやつも抜きでいいのか」と叱ると、娘が「ご飯を食べたら、またゲームをしていいから」となだめているが、「食べない」と突っぱねられている。
この論理構造はおかしくないか。
普通、条件づけは、嫌なことを克服することで褒美をもらえる。
「おもちゃを片付けたら、ジュースをあげる」といったように。
「ご飯を食べたら、ゲームをしてよい」では、ご飯を食べるのは苦痛な行為の位置づけになっている。何時から食事が義務になったのか。
子どもの頃、「お手伝いが終わったら、ご飯を食べてよい」と言われたことはあるが、「ご飯を食べたら、お手伝いをしてもよい」と言われたことはない。

世界には飢えている子どもが何億人もいる。そうしたなか、三度の食事が与えられることを感謝する気持ちを持たせなければならない。
親が家業で忙しく、兄弟姉妹が多かった親戚の家では、遊びに夢中になっていると夕食を食べ損ね、空腹を抱えたまま寝ることがたびたびだったと、みんなが集まる場では思い出が繰り返された。
嫌われるのを覚悟で「ご飯は片付けてしまえ、ゲーム機を捨ててしまえ」と宣言した。孫は仕方なく、ゲーム機の電源を落とし、食卓に座りなおした。
数分後、「この食事おいしいね」。食事後、「プラレールで遊ぶから線路作りを手伝って」とすり寄ってきた。「一人でゲームするより、じじちゃまといっしょに遊びたい」
顧問 喜多村悦史
2021年01月06日