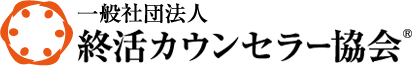怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記279 子どもの苗字
子どもの日。すべての子どもが健やかに育つようにとの思いを込めた祝日。
ではあるのだが、「男の子の日」というのが伝統的考え。女の子には3月3日があるから、これでバランスが取れている。
「そういうのは性差別であり、断固排撃する」と声を荒げる者がいるようだが、どうしてなのだろう。男は男、女は女、でいいではないか。
夫婦別姓問題で騒いでいる。どうして苗字を夫婦別々にしなければならないのか。
別姓で困る理由を与党自民党の政治家が語っている。

「女性が外で活躍するようになり、結婚を機に名前が変わると不便だから」。それならば通称と本名を使いわけばいいではないか。芸人、俳優、作家、芸術家の多くは、そのための名前を持っている。ボクだってペンネームを使うことがある。
「ひとり娘が親の会社を継いだとき、結婚して苗字が別になっていると銀行の融資が受けにくい事例があった」という意見。説明すれば済むことだし、戸籍を見せれば一発だろう。そもそも親の七光りがないと社運が傾くようでは、経営を継ぐべきではないとも言える。なお評判が悪い政治家の世襲と地盤承継だが、婿殿が後継者の場合、苗字が違ってもちゃんと当選している。説明能力の問題だろう。
「代々続く旧家で家名が途絶えるのは辛い」。夫に改姓してもらえば済むだけのこと。法律は夫婦のいずれかの姓を選択せよと言っているだけだから、発言力が強いほうの苗字にすればよかろう。
ボクもたくさんいる娘の一人くらい夫に改名させるかと期待していた。苗字を継いだ娘への遺産を多くするという戦略も考えたが、資産規模が小さいから、配分の差が魅力にならないことに気が付いた。なぜ家名継承を望むのか。突き詰めればお墓を守ってほしいから。
「お墓を買うおカネで旅行でもしようよ」。なるほどそれもそうだ。樹木葬か納骨堂にすれば、墓石建立は必要ない。お墓参りも必須ではなくなる。
後世に残すような功績もないから、個人名が残ることもない。死に際になって、それは寂しいと心残りにならないか。
「そのときは氏神神さまに寄進すれば、境内を仕切る石の垣根に氏名を彫り込んでくれるぜ」。副業で神主をしている知人が秘策を教えてくれた。
顧問 喜多村悦史
2021年05月04日