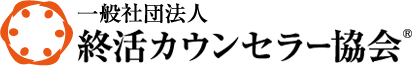怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記101 男性育児休業
育休の取得率、男性は1割未満
育児休業の取得率は、女性の83%に対し、男性はわずか7%(2019年度)。夫は外で稼ぎ、妻は家事を取り仕切る時代ではない。夫婦共稼ぎが標準モデルになって久しい。であれば家事、子育ても二人の分担になるはず。しかるにこの数値はいったい…。
![イクメングッズ!これさえ用意すればパパもイクメン☆ [ママリ]](https://cdn-mamari.imgix.net/article-cover/1200x0_57fc8783-5624-476b-b863-2acc0a010077.jpg.jpg)
一人っ子では日本の総人口は減るばかり
国民が平均して一人以上の子どもを育て上げることで総人口が維持される。男女を問わない。片親ではそのままの計算になるが、夫婦では各0.5人の計算になるから、夫婦合計では二人以上を育て上げることになる。
「一人っ子でのびのびさせてあげたい」では、総人口は世代を経るたびに半減していくのだ。
夫が家事を手伝わない家庭は少子化
「少子化社会対策白書」(内閣府)が説くところでは、夫の家事・育児時間と出生率はみごとに逆相関する。夫が休日にも何もしない家庭では、第2子以降出生は1割しかない。
夫婦と子ども二人以上家庭を増やすには、夫の家事、育児参加を増やせばよいという単純な法則になる。そこで夫の育児休業取得をとりあえず「2025年に30%」にする目標が設定された。
企業から協賛金を集め、育休取得率の高い企業に配分しては?
では男性の育児休業取得をどのようにして促進するのか。例によって総論賛成、各論反対。男性基幹社員に育児休業を取得させる企業への誘導策が必要だろう。かといって個別企業に政府助成金を支給するのは財政上も問題が多い。
総論賛成なのだから、各企業から協賛金(納付金)を出してもらう。そして目標値を上回った企業に配分(交付金)する。結果として、男性育児休業所得が低調な企業から、積極的企業への資金移転が行われる。
実務的には、納付金と交付金の差し引きを払い込むか、受け取る。障害者法定雇用率制度の応用形を実施すればよいのだ。
顧問 喜多村悦史
2020年11月09日