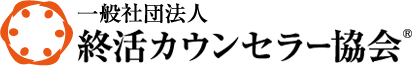怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記103 財政制度等審議会
コロナによる給付金貧乏の日本
収入に見合わない消費生活を続けることはできない。これは家計でも、政府でも同じこと。政府は通貨発行権があるのだから、いくら借金してもかまわないのだという新理論(MMT=Modern Monetary Theory)が唱えられるが、眉唾もの。
「税金いっさいなし、給付は欲しいだけ支給」という夢社会などあるはずがないだろう。
底が抜けたバケツ状態の国家財政だが、健全化は努力の積み重ねが基本。一歩ずつ財政支出を点検していくのが正道だろう。
ボクの考えは『社会保障改革への処方箋』(医薬経済社)で体系化しているが、近い提案が政府筋からも聞かれるようになってきた。そのいくつかを財政制度等審議会での議論から拾ってみよう。

① 社会保険制度になぜ公費負担?
大きな点では、社会保険制度に公費負担が繰り入れられる異質さ。高齢者医療、介護保険、国民健康保険、基礎年金では給付費の半分を公費負担。
しかも全社会保障給付費に占める公費の割合は、1990年度は25%だったが、2017年度では35%と増加。金額で50兆円(国庫35兆円、自治体15兆円)に上る(2020年度)。政府の財政再建が社会保障のスリム化にかかっていることは一目瞭然だ。
② 高齢者の医療費負担格差是正
高齢者医療や介護給付での患者負担割合の引上げも急がれる。年齢差別との声が若い世代から出ないのが不思議だ。オプジーボに代表される高額医薬品や高額医療機器の価格引き下げも避けられない。
狭い国内市場で儲けを出そうとするのが傲慢。世界でシェアを取り、国内患者に利益還元させる力を保険者も企業も持っているはずだ。
③ 児童手当等を社会保険給付化
子育てに関する児童手当などを社会保険給付にすること(例えば子ども年金と銘打つ)も必要だろう。
次世代を支える健全な子どもの養育は、国民連帯で少子化を乗り切る格好のテーマのはず。返す刀で公費の節減=財政再建に寄与することになる。
顧問 喜多村悦史
2020年11月10日