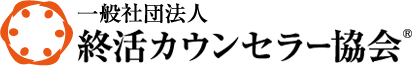怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記88 高齢就業者過去最多
「統計からみた我が国の高齢者」(2020年9月時点)を総務省が公表した。
総数3617万人で前年より30万人増。この間総人口は1億2586万人へと29万人減少しているから、高齢人口比率は28.4%から28.7%に上昇。この数値は世界一。2位はイタリアの23.3%だから、ダントツあるいは並外れての形容がふさわしい。
年代別人口比率では、年少者(15歳未満)11.9%、生産年齢(15歳以上65歳未満)59.3%。高齢者28.4%の再掲では、70歳以上22.2%、75歳以上14.9%、80歳以上9.2%、85歳以上4.9%、90歳以上1.9%、95歳以上0.5%、100歳以上0.1%。老齢年金支給年齢は何歳からが妥当か、再設定の必要が理解できよう。

その場合高齢者の就業率向上が重要だ。年々上昇して24.9%に改善し、特に65歳以上70歳未満層では48.1%になっている。ただし数値に酔ってはいけない。「月末1週間に収入を伴う仕事を1時間以上した者」はすべて就業者に含まれるから、家計維持の観点からは過大比率になっている。逆にボランティアの町内会活動などは除外されるから、生きがいでの社会貢献が反映されていない。
「働くこと=カネを得る活動」との短絡思考を政策担当者の脳内から追い出すことが必要だ。高齢者のすべてが生計に窮しているわけではない。子育てや資産形成に追われる生産年齢層と異なり、高齢者では「悠々自適は可能だが心身の健康のために社会とのつながりを求める」者が少なくない。高齢就業者の産業分類では、「卸売業、小売業」「農業、林業」などが多い。そして「農業、林業」では就業者の過半52.2%が高齢者であるという。このなかには生産物の大半が自家消費や近隣、友人に配るという人が多数いるはずだ。無為(することがない)高齢者をなくすのが政策のはずである。
顧問 喜多村悦史
2020年10月25日