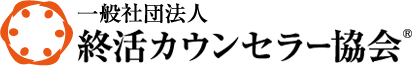怒苦打身日記 ~協会顧問 喜多村悦史のブログ~
怒苦打身日記98 公務員暑支給について
民間企業のボーナス減により公務員もダウン
人事院が国家公務員のボーナス勧告を出した。毎月支給の本給等に対する割合を4.45か月分で、前年より0.05か月分の減(節減総額200億円)にする。民間企業で業績悪化により支給額が減っている(平均4.46か月分)ことを反映したものだという。
公務員へのボーナス(賞与)支給のたびに疑問に思う。ボーナスとは何かである。Wikipediaでは、「定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことで、欧米での特別配当や報奨金に相当する」とされている。
わが国での由来は、江戸時代の商人がお盆と年末に奉公人に配った氷代や餅代にあり、明治になって三菱商会などが採用した。これは欧米と大差なしシステムだったが、太平洋戦争敗戦後のインフレへの対処として、生活給的に一律支給の色彩が強まった。
ただし労働基準法の施行通知(昭和22年9月13日発基17号)では、「労働者の勤務成績に応じて支給されるもので、定期的に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさない」としている。

公務員の評価基準を民間企業と同等にしていいのか
民間企業で賞与規定があるのは9割、支給額算定では「成果(目標)達成度」や「職務遂行能力」が評価される。事業体の収益や業務拡大への貢献を問うということだろう。
営利事業を行わない部署の公務員では、事業体の収益をボーナスに反映させることはできない。だが単純に民間の支給額に準拠ということでいいのだろうか。果たすべき職責の達成度という基準は可能なはずだ。
国家財政の収支均衡、安全保障の確保その他政策課題の実現度の評価は、国会の決算委員会や会計検査院で査定できるはず。短期で評価すべきではないとするならば、ボーナス廃止、国民への貢献度は退職金や年金加算で対応すればよいと思われる。
顧問 喜多村悦史
2020年11月04日